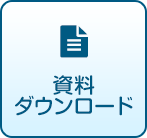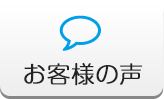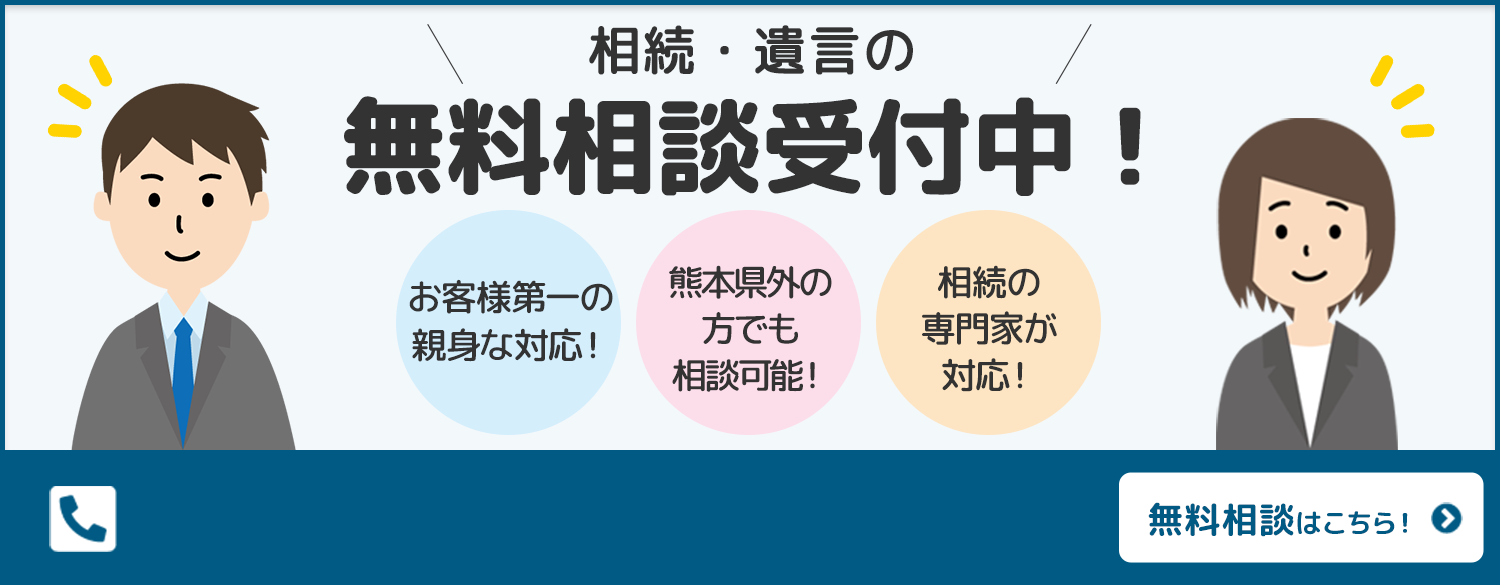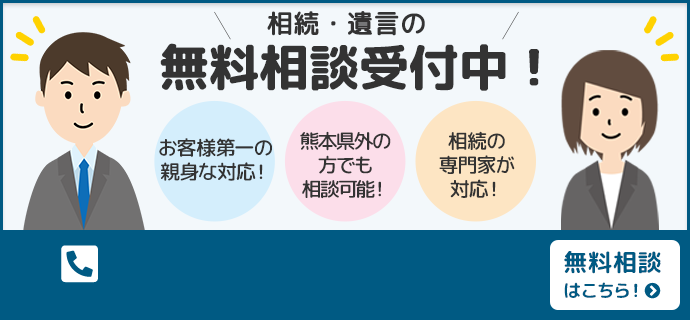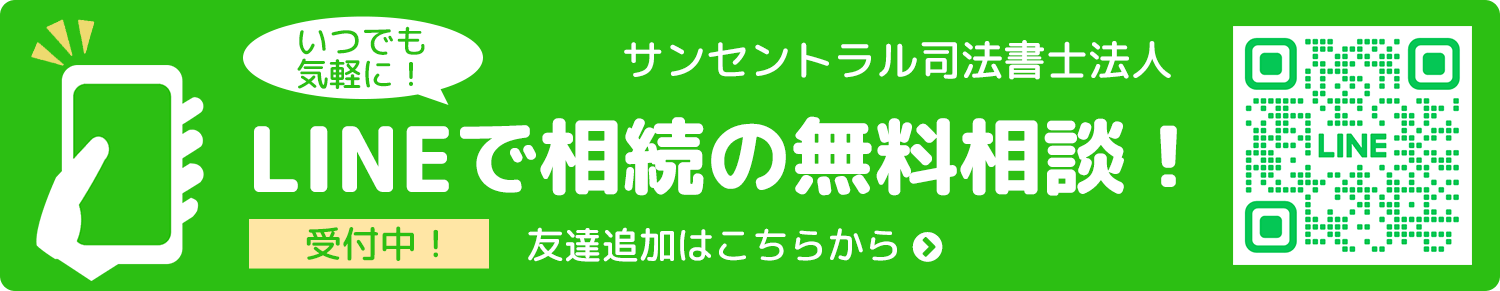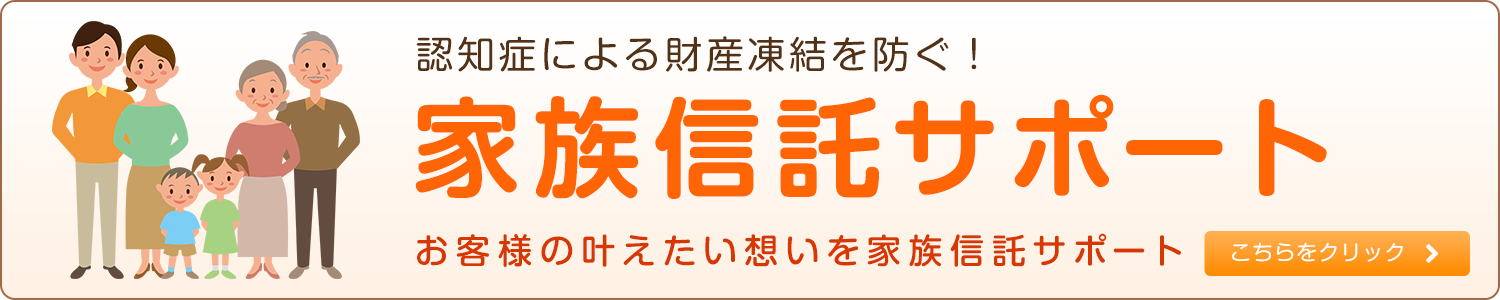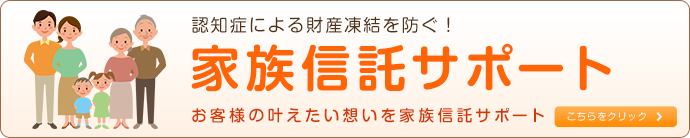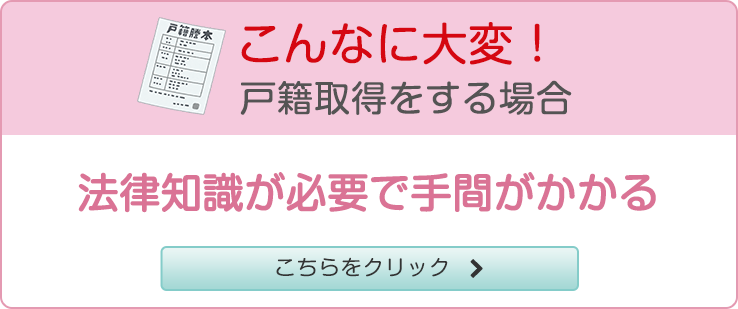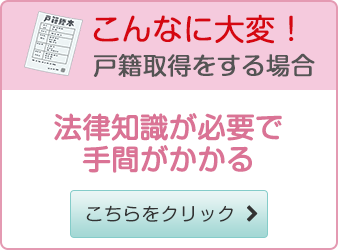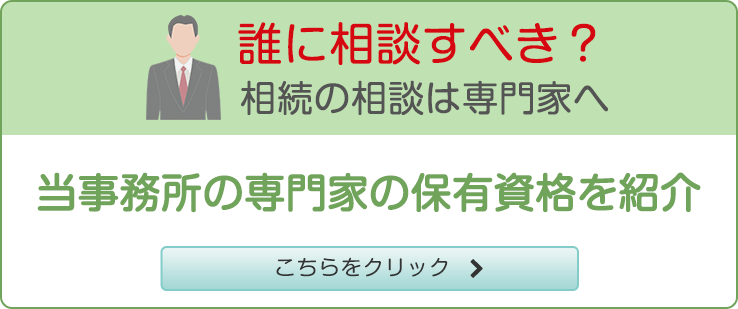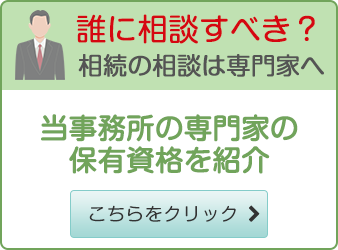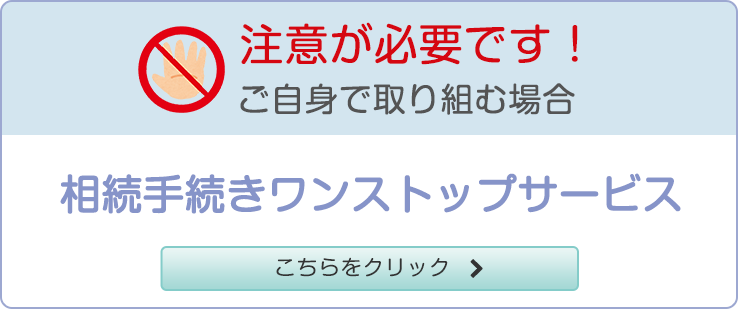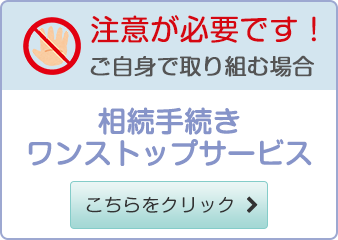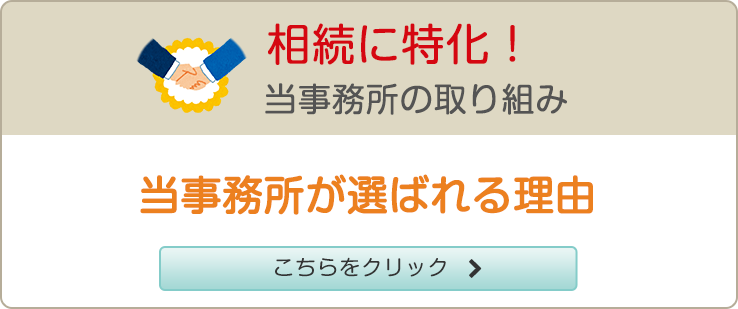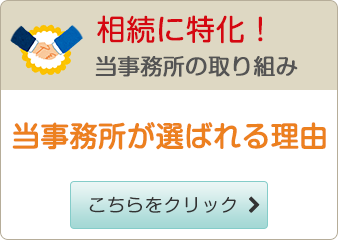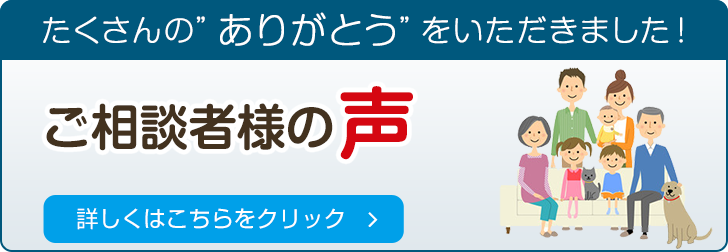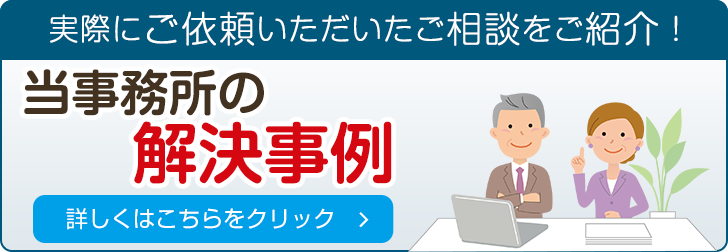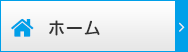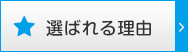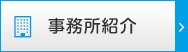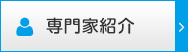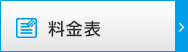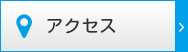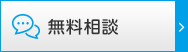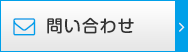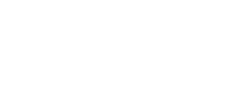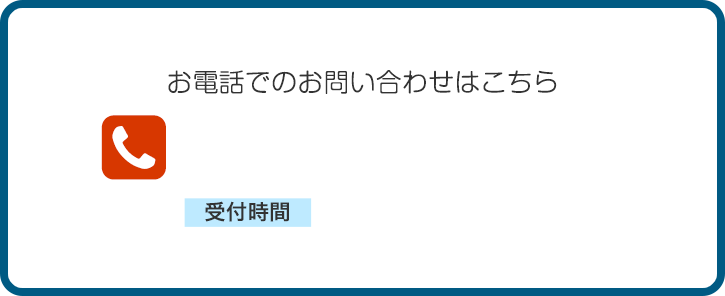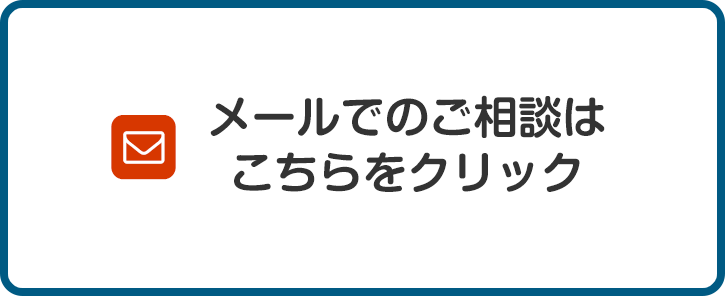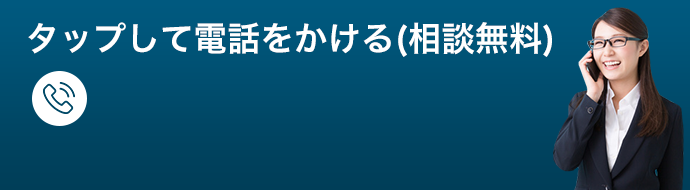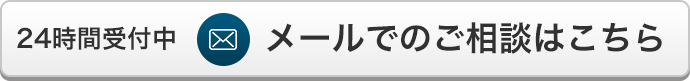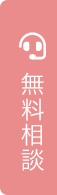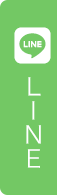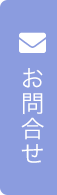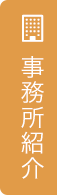【解決事例】法定相続分での相続登記後に遺言書が発見されたケース
- 2025.09.04

1. 状況
相談者:
60代、女性、熊本県在住
相談内容:
被相続人が亡くなった後、法定相続分に基づく相続登記が行われ、さらに次の世代である孫の代にまで共有名義での相続登記がなされていた不動産について、公正証書遺言書が新たに発見されました。その遺言書には、特定の人物にすべての不動産を相続させる旨が明記されており、法定相続とは異なる内容となっていました。今回の相談者は、その遺言書により相続することが指定された人物の相続人です。相談者としては、遺言書に記された通りの内容に登記を変更したうえで、最終的には不動産を売却し、換価分割したいとのご希望でした。
相談の背景:
共有不動産として名義人が複数存在し、しかも世代をまたいだ相続登記が重なっていたため、現在の登記状況は非常に複雑なものでした。そのため、遺言書に基づいた登記変更を実現するためには、関係者との連絡・合意形成、登記簿の整理、そして法務局との事前相談が不可欠な状況でした。
2. 相続手続きの設計
提案内容:
まず、公正証書遺言書に従い、遺言で指定された相続人に対して不動産の名義を変更するための登記(更正登記)を提案しました。ただし、法定相続分での登記がすでになされており、かつ次世代にまで登記が及んでいることから、単純な更正登記では済まず、名義の整理と関係者の協力が必要な状況でした。
法務局に対しては事前に照会を行い、登記の適正な手順と必要書類について確認をとりました。そのうえで、登記申請を順を追って進める計画を立案しました。具体的には、まず既存の相続登記を遺言書の内容に即した形に修正するために、各名義人や相続人との調整を行い、次に相談者への相続登記を完了させる流れです。
相続の目的:
被相続人の真意に沿った形で登記内容を是正し、相談者が単独で不動産を所有できる状態を実現した上で、売却を通じた換価分割を行うことが目的でした。最終的には相続財産の円満な処理と、複雑化した相続関係の整理が主なゴールとなります。
相続財産:
不動産(土地および建物)— 共有状態にある都市近郊の住宅地で、資産価値が比較的高く、今後の売却可能性も高い物件でした。
当事者:
- 相続人:相談者(遺言で指定された相続人の相続人)
- その他:既に相続登記されている親族複数名(孫の代も含む)
3. 相続手続きを行うメリット
具体的な効果:
相談者が主体となって、登記名義人となっていた他の親族と粘り強く連絡を取り合い、遺言書の内容に理解を得ることができました。その結果として、複雑に絡み合った登記関係を整理し、遺言書に則った登記の更正と相談者への相続登記を無事完了させることができました。
メリットの整理:
- 遺言書の有効活用: 法定相続と異なる意志が反映され、被相続人の真意を実現できた。
- 登記名義の整理: 相続登記が多世代にわたって行われていた複雑な共有状態を解消。
- 不動産の流動性向上: 登記整理後は単独名義となり、不動産の売却や有効活用が可能に。
- 家族間の合意形成: 調整を経て、法的トラブルを未然に防ぐことができた。
手続きの流れ
4. まとめ
法定相続分で登記がなされ、さらに孫の代にまで登記が及んでいた共有不動産に、公正証書遺言書が発見されたという事例です。遺言書に従い登記を是正し、最終的に相談者への単独所有に切り替えるという複雑な手続きでしたが、法務局への照会、関係者との調整を経て、無事に登記変更を完了。不動産の売却へと進むことが可能となりました。
メッセージ:
相続登記は一度済ませても、新たな事実(遺言書の発見など)によって再整理が必要となる場合があります。相続人間の関係が複雑な場合でも、法的な根拠をもとに手続きを進めることで、円滑な相続と財産の活用が可能です。遺言書がある場合は、たとえ登記が済んでいても諦めずに、まずは専門家へご相談ください。相続登記を正しく整えることが、今後のトラブル防止と資産の有効活用につながります。