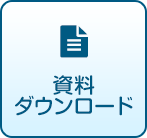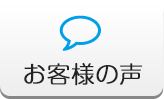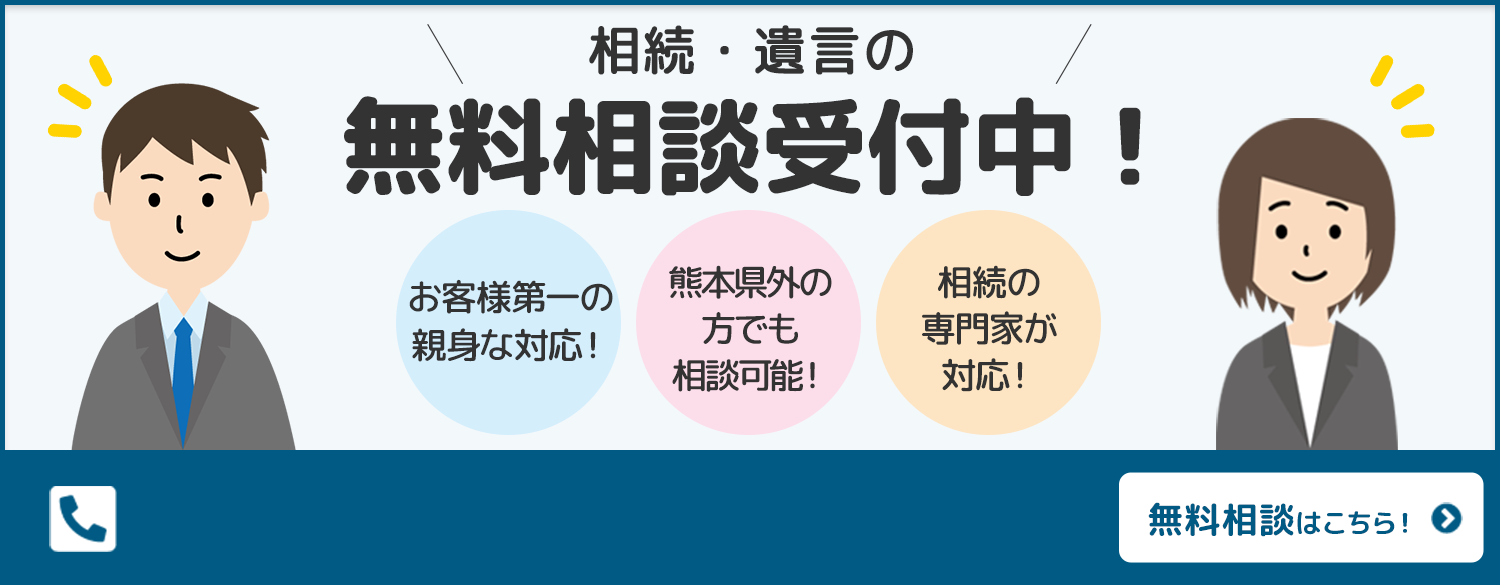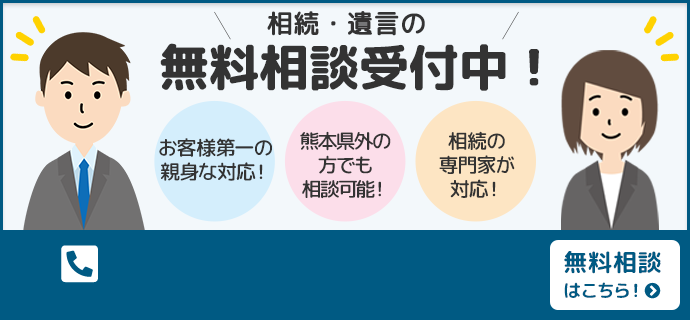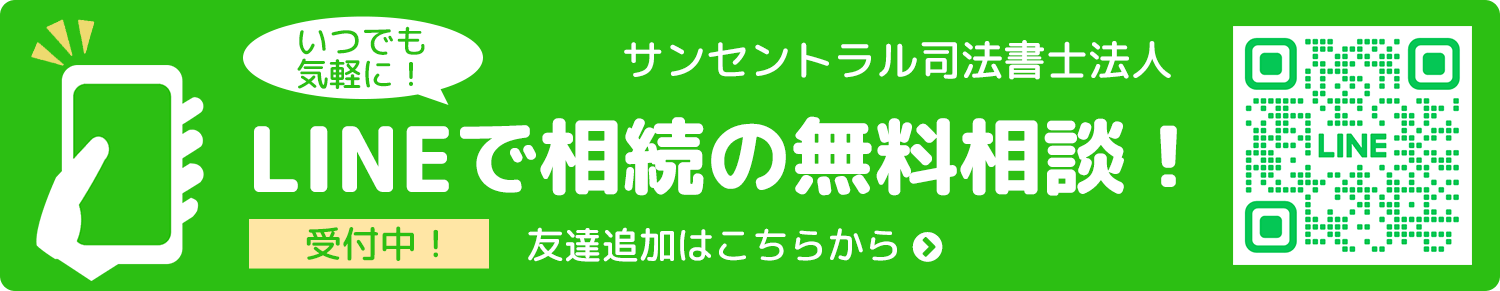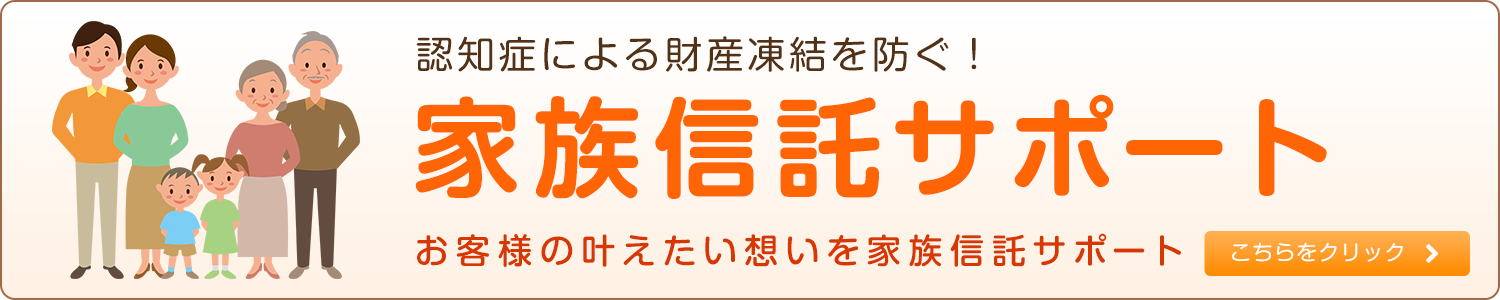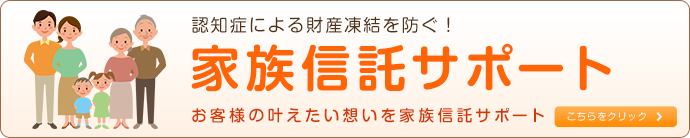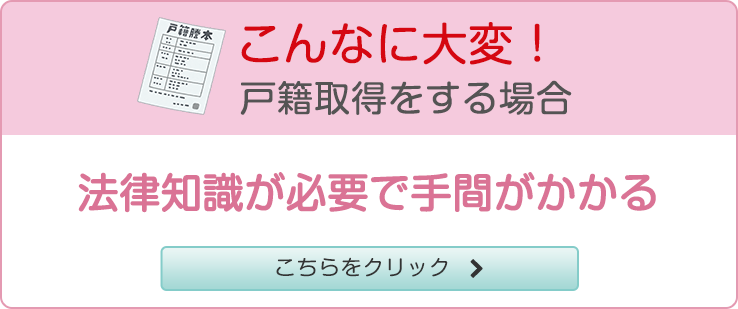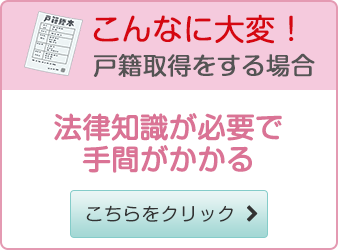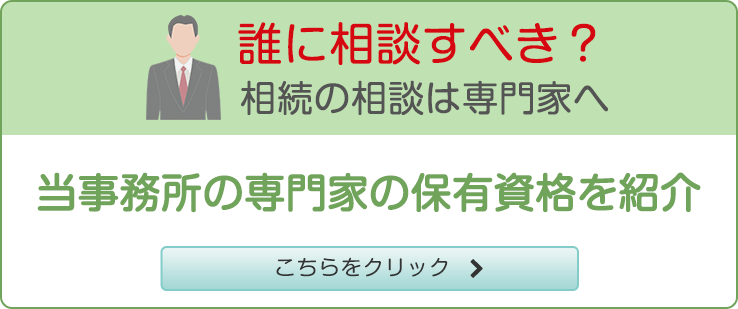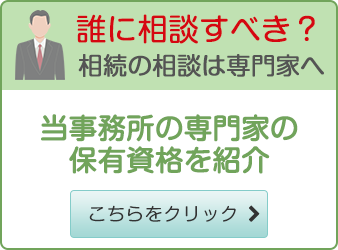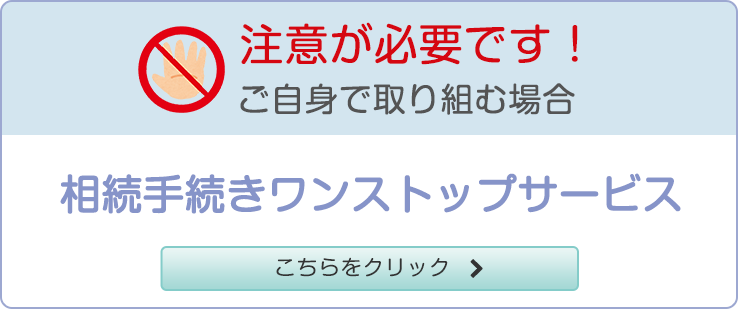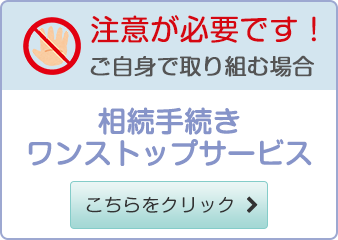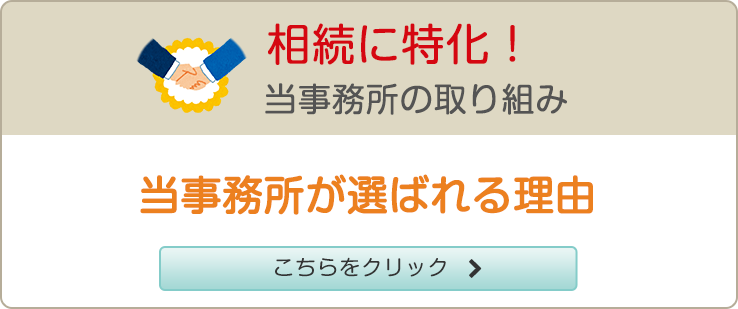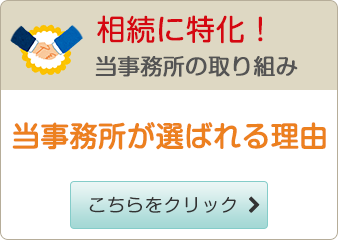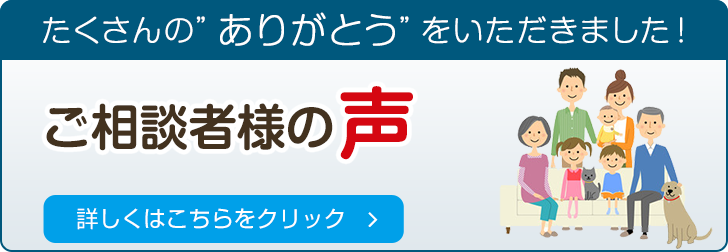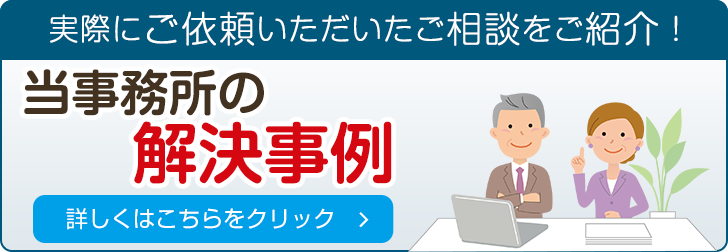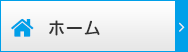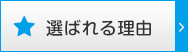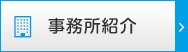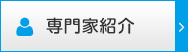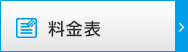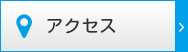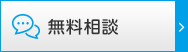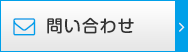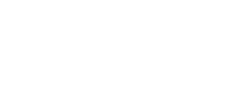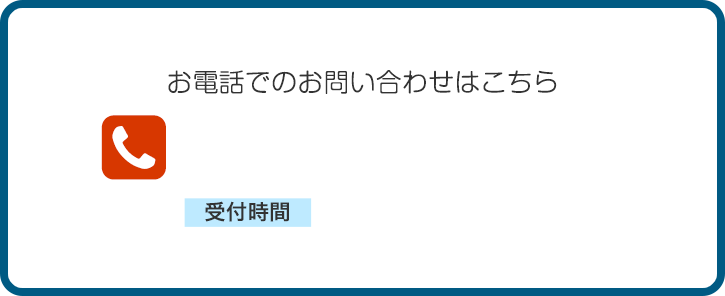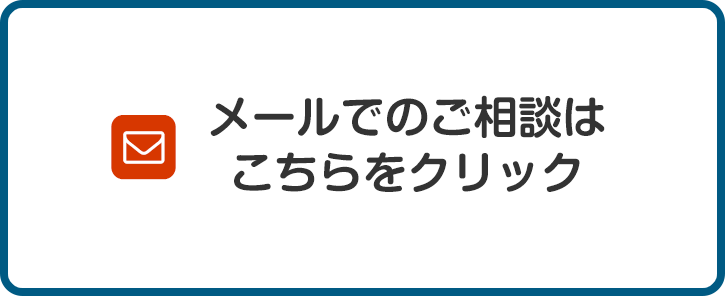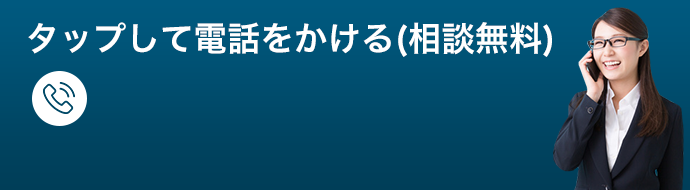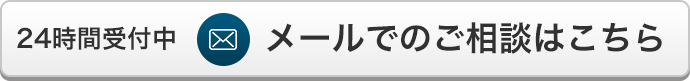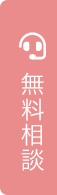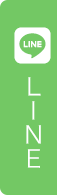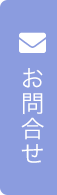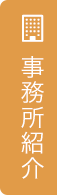【解決事例】父と長男、それぞれの名義の不動産の相続登記 換価分割
- 2025.09.04


1. 状況
今回のご相談者は、熊本市内にお住まいの70代の男性です。ご相談のきっかけは、兄(長男)が亡くなったことでした。兄名義の不動産と、既に他界している父親名義の不動産がある中で、どちらの不動産も名義変更(相続登記)がされておらず、今後の管理や売却を見据えて一括して手続きを進めたいとのご希望がありました。
相談者ご本人は三男にあたり、実際にその不動産を引き継ぎ、売却したうえで、売却代金を次男と自分とで公平に2分の1ずつに分けたいとのご意向をお持ちでした。次男は遠方に住んでおり、手続きへの関与は最小限にとどめたいという状況でもありました。
このように、複数の名義人がいる不動産の一括相続登記と、その後の売却・代金分配という、やや複雑な相続手続きが求められる案件でした。
2. 相続手続きの設計
今回のケースでは、父親名義の不動産と、兄名義の不動産のそれぞれについて、法定相続人による相続登記を行う必要がありました。
父親名義の不動産については、法定相続人である次男・三男間での遺産分割協議を行い、全ての権利を三男が相続する旨を明記した協議書を作成しました。兄(長男)の不動産については、兄が生前に独身で子もおらず、法定相続人は兄弟のみであることが確認されましたので、同様に三男が単独で相続する旨を協議し、手続きを進めました。
相続登記が完了した後は、これらの不動産を一括して売却し、売却代金を三男が一時的に受け取り、そこから次男と自分とで2分の1ずつ公平に分けるというスキームをご提案しました。
なお、金銭の分配については後日のトラブル防止のため、簡易的な覚書も作成し、お互いの確認と同意を文書化することで安心感を得られるよう配慮しました。
3. 相続手続きを行うメリット
今回の相続手続きを通じて、いくつかの大きなメリットが得られました。
まず第一に、不動産の名義をすっきりと一本化し、売却が可能な状態に整えることができた点が挙げられます。相続登記がされていないままでは売却手続きに支障をきたすため、名義変更を適切に行うことで、スムーズに不動産の換価を行うことができました。
第二に、当事者間で事前にしっかりと話し合い、協議書や覚書を作成することで、後のトラブルを未然に防ぐことができました。特に次男が遠方に住んでいたため、郵送やオンラインでのやり取りを活用し、負担がかからないよう工夫したこともスムーズな手続きにつながりました。
また、相談者としては、これまで維持管理に頭を悩ませていた不動産を整理できたことに加え、兄弟間で円満な形で財産を分け合えたという心理的な安心も得られたとのことでした。
手続きの流れは以下の通りです。
- 戸籍などの資料を収集し、相続関係を明確化
- 父名義・兄名義それぞれの遺産分割協議書を作成
- 相続登記を実施(すべて三男名義に統一)
- 不動産売却(不動産業者の選定、媒介契約、売買契約)
- 売却代金を次男と三男で2分の1ずつ分配
- 簡易的な金銭分配に関する覚書を取り交わし、手続き完了
4. まとめ
今回のケースは、「父名義」「兄名義」という複数の不動産を、一度の手続きでまとめて相続し、その後の換価分割を円満に進めた好事例でした。相続登記を怠っていると、不動産の管理や売却に支障が出るだけでなく、将来的には名義人がどんどん増えて複雑化する恐れもあります。
今回のように、早めに専門家に相談し、相続手続きを設計・実行することで、不要なトラブルを避け、スムーズに不動産を整理・売却することが可能になります。
相続は「人が亡くなったあと」の問題ではありますが、残されたご家族の未来を見据えた大切な選択でもあります。特に不動産を含む場合は、感情や立場の違いから思わぬ衝突に発展することもありますので、第三者の立場で整理・提案を行う専門家の関与は、精神的な安心材料にもなります。
相続でお困りの方は、まずは一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。相続を「負担」ではなく「整理のチャンス」として前向きにとらえることが、明るく安心できる未来への第一歩となるのです。